 |
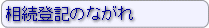 |
| �@�������J�n�B�i�푊���l�̎��S�j |
|
|
�����͔푊���l�̎��S�ɂ�蔭�����܂��B
�푊���l�̍����i�a���E�s���Y���̃v���X���Y�ƁA�؋��E�[�ŋ`�����̃}�C�i�X���Y�j�̑S�Ă𑊑��l�����p���܂��B |
| �A�⌾���̗L�����m�F���܂��B |
|
|
�Ⴆ�Δz��҂Ǝq����3�l���āA���̒���1�l�ɂ����S���Y�����̍��Y�𑊑����������Ǝv�����Ƃ��܂��B���̏ꍇ�́A�⌾���c�����Ƃɂ��A�푊���l�̍ŏI�ӎv��B�������邱�Ƃ��o���܂��B
�⌾�ɂ��A�����l�ȊO�Ɉ②�����邱�Ƃ��\�ł��B |
|
�y�⌾���̎�ށz |
|
| 1.���M�؏��⌾ |
| �i�S�����⌾�҂����M�ŏ����Ă���j |
| 2.�����؏��⌾ |
| �i�ؐl�Q�l�ȏオ������A�⌾�҂����̓��e�����ؐl�Ɍ��Ő������č쐬���܂��j |
| 3.�閧�؏��⌾ |
�i�⌾�҂��쐬�����⌾���ɏ����E������B�⌾�҂����ؐl�P�l�y�яؐl�Q�l�ȏ�̑O�ɕ������o���āA�����̈⌾���ł���|�Ǝ����E�Z�����q�ׂ���A���ؐl�����t�����ɋL�ڂ��A�S���ŏ����E���č쐬���܂��j
|
 |
| �⌾�ƕ����̕��@ |
|
�y�n�����͈⌾�̗L���ɂ��A�����̕��@���傫���ς��܂��B |
| �⌾������Ƃ��̑��� |
�S���Ȃ��������A���O�ɏ��L���Ă����y�n�⌚���ɂ��āu�N�ɏ���܂��v�ȂǂƏ��ʁE�⌾���ɂ������ꍇ�A�S���Ȃ������̈ӎv��D�悵�A�⌾���ʂ�ɓy�n�⌚������������܂��B�������A�⌾���̍쐬���@�ɂ��ẮA���@�ɍׂ����K�肪����܂��B�w�����؏��⌾�x�̏ꍇ�͖�肠��܂��A����ȊO�̈⌾���̏ꍇ�͉ƒ�ٔ����̌��F���A���̏�ł���ɐ��ƂɗL�������m�F����K�v������܂��B |
| �⌾���Ȃ������ꍇ�̑������Y�̕����@�葊���� |
�i�S���Ȃ��������⌾�����c���Ă��Ȃ������ꍇ�j�S���Ȃ��������⌾���c���ĂȂ��ꍇ�́A��{�I�ɂ͖��@�ɏ]���Ė@�葊���l�i�z��҂�q�ǂ��Ȃǁj�����Y�𑊑����܂��B |
| ��Y�������c |
�i�S���Ȃ��������⌾�����c���Ă��Ȃ������ꍇ�j�����l�S���̋��c�ɂ���č��Y�����R�ɕ����ł��܂��B���̋��c���w��Y�������c�x�Ƃ����܂��B��Y�������c�́A�@�葊�����ƈ���āA�����l1�l����Y�̑S�Ă𑊑����邱�Ƃ��\�ł��B�y�n�⌚�����܂ޕs���Y����������ꍇ�A�����l�S���̍��ӂ���ň�Y�������c���Ƃ������ʂɎ����y�сA����ɂ�鉟������܂��B |
|
|
| �B�K�v���ނ̎��W���n�߂܂��B |
|
|
�푊���l���L�̕s���Y�̌Œ莑�Y�ŕ]���ؖ����A
���ꂪ�����l�ƂȂ邩�A�ːЁE�Z���[�����đ����l���m�肳���܂��B |
| �C�@����̑������ɏ]�����@�葊���ő����B |
|
|
�܂��͑����l�Ԃœ���̑����l����Y�𑊑������Y�������c���s���B
�܂��́A�������Y�������������Ȃ�ꍇ�͑��������E���菳�F�������B |
| �D�����o�L�\�����E�����W�����}���쐬���܂��B |
|
|
��Y�������c�ɂ���đ�������ꍇ�͎Y�������c�����쐬���A�����l�������E����i����j���܂��B
�⌾���̗L���̊m�F
�⌾��������A�ƒ�ٔ����Ō��F���Ă���J�����܂��B
�i�����������؏��⌾�ł���A���̎葱�͕K�v����܂���B�j
- �����y�n���Y�E���̊T������
- �y�n���������܂��͌��菳�F�����邩�ۂ������߂Ă����܂��B
- �����l�̊m�F
- �푊���l�Ƒ����l�̖{�Вn�Ȃǂ���ːГ��{�Ȃǂ����܂��B
�푊���l�ɂ��ẮA�o�����玀�S�܂ł̑S�Ă̏��ЁE���ːЁE�ːЂ��W�߂܂��B
�����l�ɂ��ẮA�S�Ă̖@�葊���l�̌��݂̌ːЂ��W�߂܂��B
����ɁA���ۂɂ��̓y�n�𑊑�����l�̏Z���[���K�v�ł��B
- ��Y�������c���̍쐬�i��Y�������c�j
- �@�葊���l�S���̎���ƈ�ӏؖ����̓Y�t���K�v�ł��B
�i�������A�⌾��������⌾�ǂ���ɑ�������ꍇ�ɂ́A�������c���̍쐬�͕s�v�ł��B�j
- �����ł̐\���Ɣ[�t
- �푊���l�̎��S���̏����Ŗ����ɐ\���ƂƂ��ɔ[�ł��܂��B���[�E���[������Ƃ��́A���̂Ƃ��ꏏ�ɐ\�����܂��B
|
| �E�@���ǂ\���B |
|
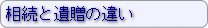 |
 |
|
�����́A�v���X�̍��Y���؋��Ȃǃ}�C�i�X�̍��Y���푊���l�i�S���Ȃ������j�̍��Y��S�ď���܂��B
�②�́A�����l�ȊO�̐l�ɑ��č��Y���^�������Ƃ��Ɉ⌾���ɂ��̎|���L�ڂ��邱�Ƃɂ���č��Y������n���܂��B
�܂��A�o�L�̂Ƃ��̓o�^�Ƌ��ł��قȂ�܂��B
�②�̏ꍇ�A�]���z��1000����20�ł����A�����ł���1000����4�ōς݂܂��B
�����݂́A�����l�ɑ���②�ɂ��Ă͑����Ɠ���1000����4�ɉ����B |